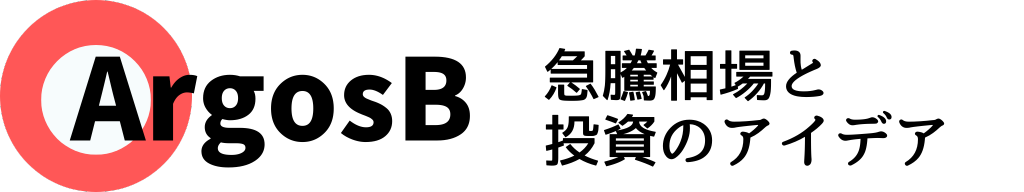日経平均が史上最高値を更新する一方、東証グロース市場や中小型株は調整色を強めています。米国でもNASDAQ100やS&P500が最高値を付けるなど世界的な株高が広がり、投資家が積極的に株を買う姿勢を鮮明にしているなか、なぜ日本のグロース市場や中小型株だけが軟調に推移しているのでしょうか。この対照的な動きは投資家にとって見過ごせないだけでなく、注目すべき展開といえるでしょう。
背景には金融政策の方向性の違いがあります。米国ではFRBが利下げを模索しており、リスク資産選好の流れが強まり、米国株の上昇を後押ししています。一方、日本では日銀が年内の利上げを検討しているとの観測が根強く、成長期待株にとっては割高感を意識させる要因となっています。その結果、海外資金は主に大型株に流入し、グロース市場や中小型株は取り残されがちです。
さらに、10月4日に実施が見込まれる自民党総裁選も市場に影響を与えます。大型株は減税や財政出動といった政策期待を織り込みやすく、海外投資家の買いを誘発する可能性があります。一方で新興市場や中小型株は直接的な恩恵が小さいものの、候補者が掲げるスタートアップ支援やAI、再生医療、インフラ再整備といった政策テーマが注目されれば、個別株物色の呼び水となるでしょう。
ここで意識したいのは循環物色の特性です。相場はまず流動性の高い大型株に資金が入り、上値余地が乏しくなると出遅れた中小型株に資金が移るのが典型的な流れです。現状は大型株優位ですが、買いが一巡した後には出遅れている新興市場や中小型株に押し目買いの好機が訪れる可能性があります。特にAI、再生医療、インフラ再整備など政策とリンクするテーマ株は、指数に先行して資金が動く展開も十分に想定されます。
総じて言えるのは、世界的な株高の中で投資家が積極的に株を買う姿勢を強めている点です。そのなかで史上最高値を更新する大型株市場の陰で調整を続けるグロース市場や中小型株は、悲観すべきではなく、むしろ次なる循環のターゲットになり得ます。足元の調整は押し目買いの好機となる可能性が高く、投資家にとって中小型株やテーマ株への戦略的なアプローチが求められる局面にあるといえるでしょう。